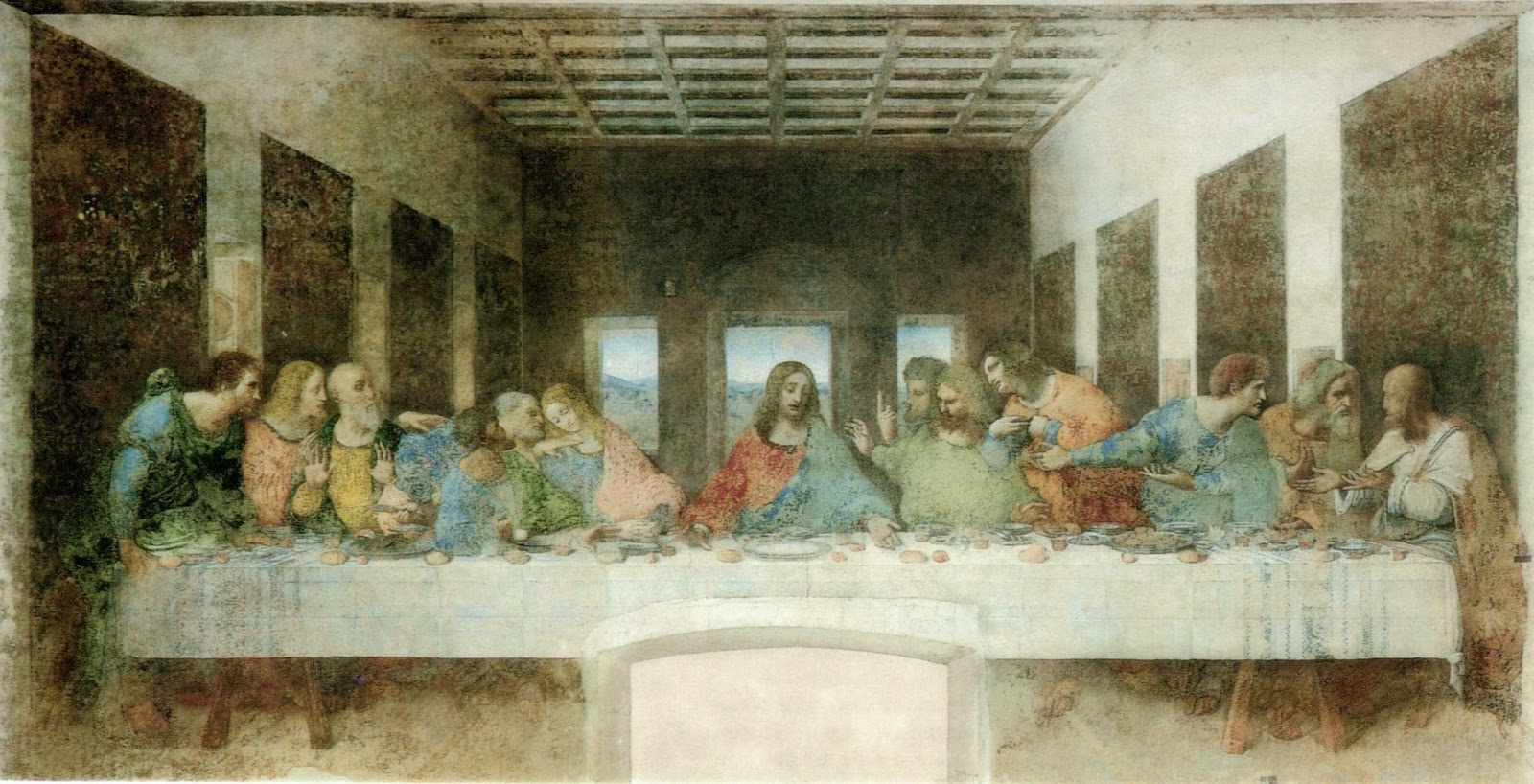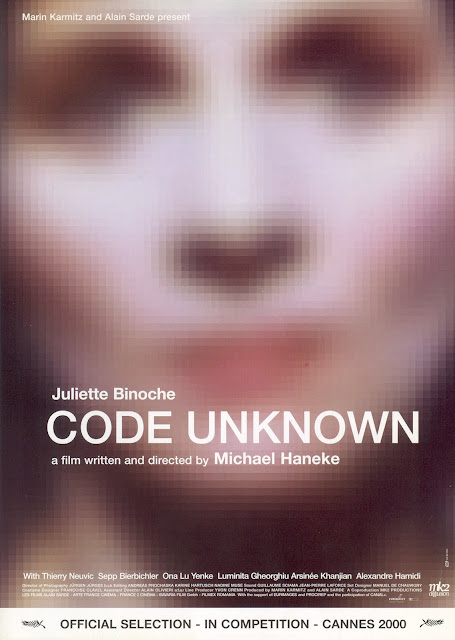『他者の苦しみへの責任』と『闇の奥』
フランシス・フォード・コッポラの名作『地獄の黙示録』の撮影が災難続きであったのは有名な話だ。まず、巨大ハリケーンに一度ならず機材のほとんどを壊される。フィリピン軍に借りる約束だったヘリコプターや爆撃機が、実戦出動のため撮影直前になんどもドタキャンされる。ハーヴェイ・カイテルの代打として選ばれた主演のマーティン・シーンは心臓発作で倒れ、デニス・ホッパーはドラッグで立ち上がることさえできない。あげくのはてにカーツ大佐役のマーロン・ブランドは、痩せるという契約を反故にしただけでなく、さらにでぶでぶに太った体でやってきて、原作はおろか脚本させ読まず、あらゆる演技を拒否したという。借金はみるみる増え、当初17週の予定だった撮影期間は61週にまで延びた。(立花隆『解読「地獄の黙示録」』)
そんなあってはならないはずの現場を、コッポラの妻エレノアが撮影していた。それが『ハート・オブ・ダークネス』というドキュメンタリーである。この映画をみると、エレノアが「本気でマーティン・シーンに殺されると思った」と語るほど、想像以上にすさまじい現場であったことがよくわかる。ブランドのスノッブで白々しい「黙示録」のラストや、ドキュメント後半ほとんど発狂状態のコッポラをみていると、むしろこっちの方が現実的な「地獄」なのでは、と思ってしまう。
コンラッドの小説『闇の奥』の舞台はアフリカ西岸の現コンゴ共和国である。物語の当時、コンゴ共和国はコンゴ自由国という呼び名の、ベルギー王レオポルド2世の私有植民地であった。
1889年にジョン・ダンロップというイギリス人が発明した空気入りゴムタイヤは、その4年前にダイムラーとベンツが発明したガソリン自動車の生産とあいまって爆発的な普及をみせる。とうぜん原料となるゴムが不足する。宗主国ベルギーの80倍の広さをもつコンゴの熱帯雨林には、原料となるゴムの木がほとんど無限のように自生していた。しかもそれを伐採する労働力はタダである。だからコンゴ川沿いにはいくつもの出張所がつくられ、アフリカ大陸のほぼ中央に位置するボヨマ滝あたりまで奥地出張所があったそうだ。(藤永茂著『「闇の奥」の奥』)
『闇の奥』もそのコンゴ川沿いに点在する出張所が舞台である。そのなかでももっとも奥地にある出張所の所長クルツは、その他のすべて出張所をあわせてもたりないほどの象牙を送ってくるという。しかし現地の噂では、クルツは原住民から神としてあがめられ、暴力で象牙をあつめているらしい。主人公マーロウは、蒸気船船長として、重病と噂されるクルツを迎えにコンゴ川をさかのぼっていく・・・。
コンラッドの『闇の奥』は、英語圏の教科書でもっとも多く使われた英文学だという。資金難でお蔵入りとなったが、かつてはオーソン・ウェルズが映画化しようとした。文学的評価は高く、おおよそが「ヨーロッパ植民地主義への批判であり人間精神の深部への鋭い洞察の書」といったものである。たしかに、取締役への出世を約束されるほど有能だったクルツが、現地人に人間性を教えるつもりで入植したアフリカコンゴの奥地で徐々に狂っていき、最後は「地獄だ! 地獄だ!」とうめきながら死んでいくさまは、ヨーロッパ植民地政策の失敗のようでもあり、人間性という曖昧な観念の崩壊のようでもあり、またコンゴが代表する人間を越えた自然への畏怖のようでもある。
しかし、読後感が無性に気持ち悪い。そもそもクルツがわからない。裏切り者の頭部を切断して柵の上に無数に飾るほど狂っているようなのだが、実に理論的で現実的で、それだけならまだいいが、まるで会社人間丸出しの台詞をはいたりもする。クルツに興味を持つマーロウの気持ちも一向につかめない。いくら読んでもクルツに同情や共感を抱いているようには思えないのだが、作中の描写ではそのように表現されていたりする。最後にクルツの婚約者に会いにいくが、婚約者の女のバカっぽい描写にどうしてもしらけてしまう。さらにクルツの最後の言葉が「地獄だ! 地獄だ!」とはどうしても言えず「あなたのお名前でした」と嘘をついたあとの自省もなんだか白々しい。ひとことで言うと、なぜクルツが狂ったのかが最後までわからないのだ。その核心がみえないから、マーロウのシンパシーも、婚約者の立場も不明瞭なままなのだ。
クルツの狂気にまったく親近感を覚えられなかったためにあまりに読後感が悪く、この悪い読後感を解消するために、この小説の日本語訳者でもある藤永茂の『「闇の奥」の奥』を読んでみた。
『「闇の奥」の奥』はまずコッポラの『地獄の黙示録』のラストがなぜ批評家受けが悪かったかからはじまる。マーロン・ブランドのダメぶりがその多くの理由だろうが、藤永はそもそも原作にあった曖昧さを、コッポラがそのまま抱え込んでしまったからだろう、という。この映画の白眉でもあるカーツの独白に出てくる「山のような切断された子どもの右腕」というエピソードが、原作の舞台であるコンゴに由来していることを指摘する。19世紀末のコンゴでは、大量の黒人奴隷を管理するため、おなじ黒人に軍隊を組織させていた。しかしその軍隊では銃弾の窃盗事件が後を絶たなかった。そこで白人統治者は、銃弾の出納を厳しく管理するため、消費した弾の数に見合うだけの死人の右手首の提出をもとめた。とうぜん、銃以外で殺し、あるいは生きたまま右手首だけを切り取って提出するものが続出した。宣教師ジョン・ハリスの妻アリスが、発明されたばかりの携帯用小型カメラで撮影した、右手首を持つ黒人奴隷の姿や、右手首だけがない現地住民の写真がいまでも残っている。コッポラと脚本家のジョン・ミリアスはこのエピソードを知って作中に取り入れたのだろう。ヨーロッパ白人が黒人原住民の右手を切り取った話が、いつのまにかベトコンがベトナムの子どもの腕を切り取る、という話に置き換わっている。ここに白人文化の問題があり、ヨーロッパのコロニアリズムの精神が隠されている、という。
次に、15世紀にポルトガルのディオゴ・カムがコンゴ川河口に人口300万の王国を「発見」してから、19世紀末にコンゴの広大な土地と人民がベルギー国王レオポルド2世の私有地になるまでの歴史と、また、そこでおこなわれていた黒人原住民の大虐殺を糾弾する人々の出現を書く。最後に、コンラッドがいかにコンゴの悲劇に対して無頓着であったか、いやむしろ、イギリス統治政策がいかにすぐれていたかの証明としてしかコンゴの惨状をみていなかったのではないか、という。著者であるコンラッド自体が、クルツの狂気の原因をアフリカの惨状にではなく、もともとアフリカにあるとされる「アフリカ的なもの」にもとめている。高橋哲哉が『記憶のエチカ』のなかで言うように、「<ヨーロッパがアフリカでおこなった恐るべき殺戮>はヨーロッパ人がではなく、アフリカ化したヨーロッパ人がおこなった」とコンラッドは理解していた。
植民地政策糾弾の書ともいわれる『闇の奥』は、本来、搾取され虐殺されるコンゴという植民地システムそのものを問題としなければならなかったのに、クルツ/マーロウという「蜥蜴の尻尾」ばかりに気をとられた結果、本当の問題であるヨーロッパの植民地主義の罪状を隠蔽することになってしまった、と藤永はいう。「コンゴの奥地でピクピクと瀕死の動きを見せている尻尾に気を奪われて、エリオット、アーレント、そして、『地獄の黙示録』のコッポラを含むほとんどの読者が蜥蜴の本体には目を向けず、コンゴの悲劇の真の根源を見なかった」。
藤永茂の『「闇の奥」の奥』は、コッポラの映画から論を進めるあたり非常に明快な「読ませる」テクニックを持ち、われわれの知らない新事実をつぎつぎに繰り出してすばやく論理の本質へと読者を誘う。著者はアルバータ大学の物理化学の名誉教授だそうである。文学専攻の人ではないが、読ませるテクニック、論の取り方は非常にうまい。むしろ専門外だからこそこう書けたのだろう。読むたびに「へえー」の連続である。まるで謎解きのように読みやすいからどんどん読み進むことができる。大きな書店では「ポストコロニアル思想」コーナーに配架されているようだが、他のポスコロとはまったく毛色がちがう。
しかし、逆を言うとその読ませるうまさが気になる部分でもある。まず冷静であること、という論理展開において重要なファクターが疑わしく感じられてしまう。ヨーロッパの植民地政策に対して、はじめから怒っているように感じられるのである。怒っている人の話だから、もう読む前に結論は見えている。怒っているから、嘘はないとしても、もしかすると読者の感情操作をしようとしているかもしれない、そう疑って身構えてしまう。鉄のように冷静な語り口でこのおなじ事実を知らされたら、かえって読者のショックは大きかったろう。しかしはじめから怒っているので、最後の結論に新鮮さがない。
多大な知識と思想的に重要な示唆をいただいておいてなんだが、そこが、おしいような気がした。光文社版訳者、黒原敏行の訳者あとがきのように「リンゴを描いた絵をミカンが描けてないと批判してもしかたない」とまでは言わないが、植民地支配をどうとらえていたかという1点だけで、作品全体の評価を決定してしまう危うさは否めない。しかしヨーロッパコロニアリズム糾弾の本なのだから、論証への入口としてコンラッドをそういう風にあつかうのはしかたがない。しかたがないが、作者が怒っているからコンラッド好きは反発するだろう。もっと冷静に論を進め、この世に数万といるコンラッド好きにもう一つの側面を開陳するきっかけになればよかったのにと、少しくやしい。
ただ、藤永の論はそれで終わるわけではない。怒ったままではあるが、ヨーロッパのコロニアリズムの精神は、現在も彼らの血と政治思想のなかで脈々と受け継がれているという。米比戦争、北ベトナム空爆、「アフリカは白人が手を引いたとたんに混沌とした暗黒大陸に逆戻りしたではないか」という思潮がヨーロッパで増加していること、「非キリスト教世界に自由と民主主義を拡大する」というブッシュ政権とネオコンの覇権主義など、糾弾の対象は現在に移り「『闇の奥』論」とは言えないところまで著者の怒りは広がる。
たしかに『闇の奥』をほんとうに額面通り「植民地政策への批判の書」とだけ理解して終わってしまっていたら、きっとその読者はヨーロッパコロニアリズム思想に則って「植民地政策って恐いよね。エリートの白人をも狂わすアフリカの大地も恐いけど」という結論で終わるだろう。そういう無意識で薄い罠は、われわれの非欧米へのまなざしをつねに決定づけている。被植民地アフリカへのシンパシーそのものが、われわれがその裏側の真実をしるまなざしを婉曲しているのである。
医療人類学という聞き慣れないジャンルで積極的な発言を繰り返すアーサー・クラインマン他が寄稿した論文集『他者の苦しみへの責任』がみすず書房から刊行された。
6つの論文からなる本書の第1章、アーサー・クラインマンの『苦しむ人々・衝撃的な映像ーー現在における苦しみの文化的流用』を読んでも、藤永茂のいう「現代のコロニアリズム」がメディアのなかにいまだいきづいていることに気がつくだろう。
1993年にスーダンで撮影されたケヴィン・カーターの写真『ハゲタカと少女』は同年のピューリッツァー賞を受賞した。この衝撃的な写真によってアメリカの人々は困惑し、なにかしたいという思いに駆られたその一方で、撮影者であるケヴィン・カーターにたいして「なぜ助けなかったのか」という非難がおこる。「ケヴィン・カーターはこのハゲタカと一緒である」とまで言う人もいた。ところが撮影者であったケヴィン・カーターが自殺してしまうことで、この写真の持つ意味は複雑なものになる。本来、撮影者であり白人であるカメラマンと、その向こうにうずくまるスーダンの少女とのあいだには決定的に大きな溝があった。写真の下に小さく書かれたキャプションでしかなかった撮影者は、しかし自殺することでこの写真のなかで展開される物語の一部となり、登場人物となったのだ。そこでは「主体と客体を二分していた壁は崩れおち、事態は複雑なものになる」。そのなかでは、ケヴィン・カーターという撮影者が『闇の奥』の世界のなかに立つことになる。まるでマーロウのように。
しかし、もしケヴィン・カーターが自殺していなければ、われわれはどうしていたのだろうか。絶対的に安全な位置にいて、毎日、世界中の「苦しみ」が商品として売り買いされ、メディア素材として流通し、苦しみを測る尺度として商品価値を問われる映像に毎日さらされた日常のなかで、われわれはこのスーダンの少女とのあいだの、「決定的に大きな溝」を埋める努力をしたのだろうか。そもそもそのような溝の存在すら気づかなかったからこそ、ニューヨークタイムズをみた読者はケヴィン・カーターを非難したのではなかったか。
他者の苦しみをメディアという流通商品を通してみる以上、スーダンの少女に対するわれわれの同情は、つねにコロニアリズムの残滓でおおわれた見方である。この死にゆく少女ひとりをみて、この人たちは自分で身をまもることができない、つねに誰かが「外からの力」でその世界を変えなければならないし、その惨状を誰かが伝えなければ彼らには訴える方法さえないと、そう思う。しかし現実において、苦しみはこの少女ひとりが背負っているものではない。多くの人間があつまったローカルのできごとである。またわれわれは、つねに苦しみをひとつのものとして扱おうとする。スーダンの少女の苦しみは、他のスーダン人の苦しみとも違うし、コンゴのそれともとうぜん違う。アーサー・クラインマンは言う。
「苦しみを本質主義的、自然主義的にとらえること、そして感傷的に扱うことは、絶対に避けなければならない。苦しみが軽んじられる社会もあれば、大きな意味を与えられる社会もある。歴史家や文化人類学たちは、苦しみの経験がもつ意味がさまざまであることを示している。人々の苦しみ方は、それぞれちがうのである。それは、どう生きるか、なにを問題にするか、重大な問題にどう対処するかが、人によってちがうのと同じである。同じコミュニティのなかでも、苦痛の受け止めかたや表し方は異なっている。極度の苦しみーーナチスの死の収容所やカンボジアの大虐殺などを生き延びた人々の苦しみーーは、貧困や病気のような『通常の』苦しみとは異質のものである」
また、アフリカの苦しみをみることで得られるメッセージのもう一つは、「西洋にもさまざまな混乱はあるが、それでも、このアフリカの社会よりはわれわれのほうがましだ」というコンラッドの時代の発想とさして違いのないものである。むしろサイードがいう「帝国主義に冒されたコンラッドの思想的限界」が、今もそのままの姿でわれわれの家庭にまで直接送られてくるのだ。
そのようなメディアが資本価値として日常的に流通する世界では、表面的には善意、同情、貢献といった言葉で表現できるこころの動きを視聴者が持ったとしても、そもそもそのこころの動きをおこさせる「価値」は、メディアの持つセンセーショナリズムが決定しているのである。1993年4月9日付けのニューヨークタイムズに、バングラデシュの赤線地帯で撮られた幼児売春婦の写真が掲載された。たぶん14、5才のその少女は、胸をはだけた服を着て、ほつれた髪に、たくさんのイヤリングやネックレスをつけて、ロリータ風の笑顔を浮かべて立っている。見出しには「セックスマーケットーー餌食にされる世界の子どもたち」と書かれているが、「しかし、この写真は、一流新聞に掲載されていなければ、児童ポルノになってしまうだろう」とクラインマンは書く。もはやわれわれは、思春期の少女が売春しているというテキストの記事だけでは反応しない体質になっているのだ。より高度で、より過酷な苦しみでなければ、その存在さえ無視してしまう。「このようにメディアは、効果的な写真を提示することによって、批判する対象に絡め取られてしまうのである」。
マイケル・シャロピは言う。
ケヴィン・カーターに関する過去記事:「フィクションとノンフィクションの境界」
.
そんなあってはならないはずの現場を、コッポラの妻エレノアが撮影していた。それが『ハート・オブ・ダークネス』というドキュメンタリーである。この映画をみると、エレノアが「本気でマーティン・シーンに殺されると思った」と語るほど、想像以上にすさまじい現場であったことがよくわかる。ブランドのスノッブで白々しい「黙示録」のラストや、ドキュメント後半ほとんど発狂状態のコッポラをみていると、むしろこっちの方が現実的な「地獄」なのでは、と思ってしまう。
このタイトルの『ハート・オブ・ダークネス』、日本語訳にすると「闇の奥」となる。『地獄の黙示録』の原作で、ジョセフ・コンラッドの小説『闇の奥』のことである。
コンラッドの小説『闇の奥』の舞台はアフリカ西岸の現コンゴ共和国である。物語の当時、コンゴ共和国はコンゴ自由国という呼び名の、ベルギー王レオポルド2世の私有植民地であった。
1889年にジョン・ダンロップというイギリス人が発明した空気入りゴムタイヤは、その4年前にダイムラーとベンツが発明したガソリン自動車の生産とあいまって爆発的な普及をみせる。とうぜん原料となるゴムが不足する。宗主国ベルギーの80倍の広さをもつコンゴの熱帯雨林には、原料となるゴムの木がほとんど無限のように自生していた。しかもそれを伐採する労働力はタダである。だからコンゴ川沿いにはいくつもの出張所がつくられ、アフリカ大陸のほぼ中央に位置するボヨマ滝あたりまで奥地出張所があったそうだ。(藤永茂著『「闇の奥」の奥』)
『闇の奥』もそのコンゴ川沿いに点在する出張所が舞台である。そのなかでももっとも奥地にある出張所の所長クルツは、その他のすべて出張所をあわせてもたりないほどの象牙を送ってくるという。しかし現地の噂では、クルツは原住民から神としてあがめられ、暴力で象牙をあつめているらしい。主人公マーロウは、蒸気船船長として、重病と噂されるクルツを迎えにコンゴ川をさかのぼっていく・・・。
コンラッドの『闇の奥』は、英語圏の教科書でもっとも多く使われた英文学だという。資金難でお蔵入りとなったが、かつてはオーソン・ウェルズが映画化しようとした。文学的評価は高く、おおよそが「ヨーロッパ植民地主義への批判であり人間精神の深部への鋭い洞察の書」といったものである。たしかに、取締役への出世を約束されるほど有能だったクルツが、現地人に人間性を教えるつもりで入植したアフリカコンゴの奥地で徐々に狂っていき、最後は「地獄だ! 地獄だ!」とうめきながら死んでいくさまは、ヨーロッパ植民地政策の失敗のようでもあり、人間性という曖昧な観念の崩壊のようでもあり、またコンゴが代表する人間を越えた自然への畏怖のようでもある。
しかし、読後感が無性に気持ち悪い。そもそもクルツがわからない。裏切り者の頭部を切断して柵の上に無数に飾るほど狂っているようなのだが、実に理論的で現実的で、それだけならまだいいが、まるで会社人間丸出しの台詞をはいたりもする。クルツに興味を持つマーロウの気持ちも一向につかめない。いくら読んでもクルツに同情や共感を抱いているようには思えないのだが、作中の描写ではそのように表現されていたりする。最後にクルツの婚約者に会いにいくが、婚約者の女のバカっぽい描写にどうしてもしらけてしまう。さらにクルツの最後の言葉が「地獄だ! 地獄だ!」とはどうしても言えず「あなたのお名前でした」と嘘をついたあとの自省もなんだか白々しい。ひとことで言うと、なぜクルツが狂ったのかが最後までわからないのだ。その核心がみえないから、マーロウのシンパシーも、婚約者の立場も不明瞭なままなのだ。
クルツの狂気にまったく親近感を覚えられなかったためにあまりに読後感が悪く、この悪い読後感を解消するために、この小説の日本語訳者でもある藤永茂の『「闇の奥」の奥』を読んでみた。
『「闇の奥」の奥』はまずコッポラの『地獄の黙示録』のラストがなぜ批評家受けが悪かったかからはじまる。マーロン・ブランドのダメぶりがその多くの理由だろうが、藤永はそもそも原作にあった曖昧さを、コッポラがそのまま抱え込んでしまったからだろう、という。この映画の白眉でもあるカーツの独白に出てくる「山のような切断された子どもの右腕」というエピソードが、原作の舞台であるコンゴに由来していることを指摘する。19世紀末のコンゴでは、大量の黒人奴隷を管理するため、おなじ黒人に軍隊を組織させていた。しかしその軍隊では銃弾の窃盗事件が後を絶たなかった。そこで白人統治者は、銃弾の出納を厳しく管理するため、消費した弾の数に見合うだけの死人の右手首の提出をもとめた。とうぜん、銃以外で殺し、あるいは生きたまま右手首だけを切り取って提出するものが続出した。宣教師ジョン・ハリスの妻アリスが、発明されたばかりの携帯用小型カメラで撮影した、右手首を持つ黒人奴隷の姿や、右手首だけがない現地住民の写真がいまでも残っている。コッポラと脚本家のジョン・ミリアスはこのエピソードを知って作中に取り入れたのだろう。ヨーロッパ白人が黒人原住民の右手を切り取った話が、いつのまにかベトコンがベトナムの子どもの腕を切り取る、という話に置き換わっている。ここに白人文化の問題があり、ヨーロッパのコロニアリズムの精神が隠されている、という。
次に、15世紀にポルトガルのディオゴ・カムがコンゴ川河口に人口300万の王国を「発見」してから、19世紀末にコンゴの広大な土地と人民がベルギー国王レオポルド2世の私有地になるまでの歴史と、また、そこでおこなわれていた黒人原住民の大虐殺を糾弾する人々の出現を書く。最後に、コンラッドがいかにコンゴの悲劇に対して無頓着であったか、いやむしろ、イギリス統治政策がいかにすぐれていたかの証明としてしかコンゴの惨状をみていなかったのではないか、という。著者であるコンラッド自体が、クルツの狂気の原因をアフリカの惨状にではなく、もともとアフリカにあるとされる「アフリカ的なもの」にもとめている。高橋哲哉が『記憶のエチカ』のなかで言うように、「<ヨーロッパがアフリカでおこなった恐るべき殺戮>はヨーロッパ人がではなく、アフリカ化したヨーロッパ人がおこなった」とコンラッドは理解していた。
植民地政策糾弾の書ともいわれる『闇の奥』は、本来、搾取され虐殺されるコンゴという植民地システムそのものを問題としなければならなかったのに、クルツ/マーロウという「蜥蜴の尻尾」ばかりに気をとられた結果、本当の問題であるヨーロッパの植民地主義の罪状を隠蔽することになってしまった、と藤永はいう。「コンゴの奥地でピクピクと瀕死の動きを見せている尻尾に気を奪われて、エリオット、アーレント、そして、『地獄の黙示録』のコッポラを含むほとんどの読者が蜥蜴の本体には目を向けず、コンゴの悲劇の真の根源を見なかった」。
藤永茂の『「闇の奥」の奥』は、コッポラの映画から論を進めるあたり非常に明快な「読ませる」テクニックを持ち、われわれの知らない新事実をつぎつぎに繰り出してすばやく論理の本質へと読者を誘う。著者はアルバータ大学の物理化学の名誉教授だそうである。文学専攻の人ではないが、読ませるテクニック、論の取り方は非常にうまい。むしろ専門外だからこそこう書けたのだろう。読むたびに「へえー」の連続である。まるで謎解きのように読みやすいからどんどん読み進むことができる。大きな書店では「ポストコロニアル思想」コーナーに配架されているようだが、他のポスコロとはまったく毛色がちがう。
しかし、逆を言うとその読ませるうまさが気になる部分でもある。まず冷静であること、という論理展開において重要なファクターが疑わしく感じられてしまう。ヨーロッパの植民地政策に対して、はじめから怒っているように感じられるのである。怒っている人の話だから、もう読む前に結論は見えている。怒っているから、嘘はないとしても、もしかすると読者の感情操作をしようとしているかもしれない、そう疑って身構えてしまう。鉄のように冷静な語り口でこのおなじ事実を知らされたら、かえって読者のショックは大きかったろう。しかしはじめから怒っているので、最後の結論に新鮮さがない。
多大な知識と思想的に重要な示唆をいただいておいてなんだが、そこが、おしいような気がした。光文社版訳者、黒原敏行の訳者あとがきのように「リンゴを描いた絵をミカンが描けてないと批判してもしかたない」とまでは言わないが、植民地支配をどうとらえていたかという1点だけで、作品全体の評価を決定してしまう危うさは否めない。しかしヨーロッパコロニアリズム糾弾の本なのだから、論証への入口としてコンラッドをそういう風にあつかうのはしかたがない。しかたがないが、作者が怒っているからコンラッド好きは反発するだろう。もっと冷静に論を進め、この世に数万といるコンラッド好きにもう一つの側面を開陳するきっかけになればよかったのにと、少しくやしい。
ただ、藤永の論はそれで終わるわけではない。怒ったままではあるが、ヨーロッパのコロニアリズムの精神は、現在も彼らの血と政治思想のなかで脈々と受け継がれているという。米比戦争、北ベトナム空爆、「アフリカは白人が手を引いたとたんに混沌とした暗黒大陸に逆戻りしたではないか」という思潮がヨーロッパで増加していること、「非キリスト教世界に自由と民主主義を拡大する」というブッシュ政権とネオコンの覇権主義など、糾弾の対象は現在に移り「『闇の奥』論」とは言えないところまで著者の怒りは広がる。
たしかに『闇の奥』をほんとうに額面通り「植民地政策への批判の書」とだけ理解して終わってしまっていたら、きっとその読者はヨーロッパコロニアリズム思想に則って「植民地政策って恐いよね。エリートの白人をも狂わすアフリカの大地も恐いけど」という結論で終わるだろう。そういう無意識で薄い罠は、われわれの非欧米へのまなざしをつねに決定づけている。被植民地アフリカへのシンパシーそのものが、われわれがその裏側の真実をしるまなざしを婉曲しているのである。
医療人類学という聞き慣れないジャンルで積極的な発言を繰り返すアーサー・クラインマン他が寄稿した論文集『他者の苦しみへの責任』がみすず書房から刊行された。
6つの論文からなる本書の第1章、アーサー・クラインマンの『苦しむ人々・衝撃的な映像ーー現在における苦しみの文化的流用』を読んでも、藤永茂のいう「現代のコロニアリズム」がメディアのなかにいまだいきづいていることに気がつくだろう。
1993年にスーダンで撮影されたケヴィン・カーターの写真『ハゲタカと少女』は同年のピューリッツァー賞を受賞した。この衝撃的な写真によってアメリカの人々は困惑し、なにかしたいという思いに駆られたその一方で、撮影者であるケヴィン・カーターにたいして「なぜ助けなかったのか」という非難がおこる。「ケヴィン・カーターはこのハゲタカと一緒である」とまで言う人もいた。ところが撮影者であったケヴィン・カーターが自殺してしまうことで、この写真の持つ意味は複雑なものになる。本来、撮影者であり白人であるカメラマンと、その向こうにうずくまるスーダンの少女とのあいだには決定的に大きな溝があった。写真の下に小さく書かれたキャプションでしかなかった撮影者は、しかし自殺することでこの写真のなかで展開される物語の一部となり、登場人物となったのだ。そこでは「主体と客体を二分していた壁は崩れおち、事態は複雑なものになる」。そのなかでは、ケヴィン・カーターという撮影者が『闇の奥』の世界のなかに立つことになる。まるでマーロウのように。
しかし、もしケヴィン・カーターが自殺していなければ、われわれはどうしていたのだろうか。絶対的に安全な位置にいて、毎日、世界中の「苦しみ」が商品として売り買いされ、メディア素材として流通し、苦しみを測る尺度として商品価値を問われる映像に毎日さらされた日常のなかで、われわれはこのスーダンの少女とのあいだの、「決定的に大きな溝」を埋める努力をしたのだろうか。そもそもそのような溝の存在すら気づかなかったからこそ、ニューヨークタイムズをみた読者はケヴィン・カーターを非難したのではなかったか。
他者の苦しみをメディアという流通商品を通してみる以上、スーダンの少女に対するわれわれの同情は、つねにコロニアリズムの残滓でおおわれた見方である。この死にゆく少女ひとりをみて、この人たちは自分で身をまもることができない、つねに誰かが「外からの力」でその世界を変えなければならないし、その惨状を誰かが伝えなければ彼らには訴える方法さえないと、そう思う。しかし現実において、苦しみはこの少女ひとりが背負っているものではない。多くの人間があつまったローカルのできごとである。またわれわれは、つねに苦しみをひとつのものとして扱おうとする。スーダンの少女の苦しみは、他のスーダン人の苦しみとも違うし、コンゴのそれともとうぜん違う。アーサー・クラインマンは言う。
「苦しみを本質主義的、自然主義的にとらえること、そして感傷的に扱うことは、絶対に避けなければならない。苦しみが軽んじられる社会もあれば、大きな意味を与えられる社会もある。歴史家や文化人類学たちは、苦しみの経験がもつ意味がさまざまであることを示している。人々の苦しみ方は、それぞれちがうのである。それは、どう生きるか、なにを問題にするか、重大な問題にどう対処するかが、人によってちがうのと同じである。同じコミュニティのなかでも、苦痛の受け止めかたや表し方は異なっている。極度の苦しみーーナチスの死の収容所やカンボジアの大虐殺などを生き延びた人々の苦しみーーは、貧困や病気のような『通常の』苦しみとは異質のものである」
また、アフリカの苦しみをみることで得られるメッセージのもう一つは、「西洋にもさまざまな混乱はあるが、それでも、このアフリカの社会よりはわれわれのほうがましだ」というコンラッドの時代の発想とさして違いのないものである。むしろサイードがいう「帝国主義に冒されたコンラッドの思想的限界」が、今もそのままの姿でわれわれの家庭にまで直接送られてくるのだ。
そのようなメディアが資本価値として日常的に流通する世界では、表面的には善意、同情、貢献といった言葉で表現できるこころの動きを視聴者が持ったとしても、そもそもそのこころの動きをおこさせる「価値」は、メディアの持つセンセーショナリズムが決定しているのである。1993年4月9日付けのニューヨークタイムズに、バングラデシュの赤線地帯で撮られた幼児売春婦の写真が掲載された。たぶん14、5才のその少女は、胸をはだけた服を着て、ほつれた髪に、たくさんのイヤリングやネックレスをつけて、ロリータ風の笑顔を浮かべて立っている。見出しには「セックスマーケットーー餌食にされる世界の子どもたち」と書かれているが、「しかし、この写真は、一流新聞に掲載されていなければ、児童ポルノになってしまうだろう」とクラインマンは書く。もはやわれわれは、思春期の少女が売春しているというテキストの記事だけでは反応しない体質になっているのだ。より高度で、より過酷な苦しみでなければ、その存在さえ無視してしまう。「このようにメディアは、効果的な写真を提示することによって、批判する対象に絡め取られてしまうのである」。
マイケル・シャロピは言う。
表象は現実ではない。しかし、現実はそのままたち現れることはなく、つねになんらかの表象をとおして、われわれに示される。表象を現実の模倣とみなすのは間違いである。現実は、慣習、行為、出来事の積み重ねによって作り上げられるのである。それは、個人の意識が日常的に作りあげるものではなくて、長年にわたって、事物、人々の意識、社会構造に深く刻み込まれものである。なのに、非西洋人であるわれわれでさえコンラッドの小説を正しく評価することができず、教師はどこから出来上がったきたのかさえわからない歴史を子どもたちに教え、世界の苦しみをどん欲に消費し、植民地主義は絶滅したと思い込み、またあらたなコロニアリズムに毎日少しずつ荷担しているのである。
20世紀が終わろうとしているいま、過去がその役割りを失った世界がどういうものなのか、初めてわかってきた。それは、人間を生まれてから死ぬまで個別的・集団的に導いてきた古い地図やチャートが、われわれの行く手にある土地の地形や海の航路をもはや示さない世界、われわれがどこに行こうとしているのか(あるいは行かなければならないのか)わからない世界なのである。
ケヴィン・カーターに関する過去記事:「フィクションとノンフィクションの境界」
.